「東アジアの思想」という話-33
【仏教】
《中国の仏教》
仏教は、後漢初期には中国に流入していたようです。
儒教は現実的な教えですが、仏教は深遠です。教義も戒律も受け入れやすかったので、中央アジアに広がりました。
儒教は思想や生活まで支配していましたから、積極的な布教はできませんでした。やがて、後漢が衰えるようになり、仏教は中華に根を下ろしはじめます。
仏教は、泥中から蓮の花が咲く宗教ですから、そうした不安や混乱のうちに種が蒔かれたのでしょう。
魏晋では、老荘思想に結びつきます。これは、仏教が中国に入ってくるときの翻訳に、『老子』『荘子』『中庸』『淮南子』などからの言葉が使われたからです。
cf.
『「東アジアの思想」という話-25』【『荘子』の思想的世界-4】
鳩摩羅什(くまらじゅう)がだいたいこの時代ですね。『法華経』『阿弥陀経』『中論』『大智度論』『成実論』などを漢訳しています。
中でも、龍樹(りゅうじゅ)の『中論』は、世界を一新させてしまいます。龍樹(ナーガールジュナ)については、別の機会にしましょう。
魏晋・南朝の貴族はこぞって寄進しました。その数は実に「四百八十寺」だとか……。北の五胡十六国・北朝も似たようなものです。
とはいえ、仏教は利するためだけの善行は無視しますので、滅んでしまいます。
《菩提達磨》
南朝の梁の武帝は深く仏教を信心しましたが、悟りに機することなく、幽閉されて没しました。
武帝は、菩提達磨(ぼだいだるま)に聞きました。
武帝「あんなことやこんなことも、いっぱいした。何の功徳があるかね?」
菩提達磨「まったく功徳はありません」
武帝「どうして功徳がないのか?」
菩提達磨「煩悩の種を蒔いているだけですからね」
武帝「では、どういったものが功徳になるのか?」
菩提達磨「〈空(くう)〉です。そうした功徳は、この世界に求めてはいけないのです」
武帝「最初から教えくれないか……」
菩提達磨「〈空〉とは、何もないことです」
武帝「では、あなたは誰なのだ?」
菩提達磨「識(し)りません」
何を言っているのか分からない禅問答のようですが、菩提達磨こそ禅の創始者です。
かいつまんで解説すると、梁の武帝は形だけ信仰していて、本質を知らなかった訳です。本人は一生懸命「功徳を受けるための善行」をしていました。そんな見返りを求めている人に、仏が何を与えるというのでしょうか。
《四苦八苦》
仏陀は、人には生・老・病・死――四つの苦しみがあると説きました。
この四苦に、愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五陰盛苦の四つを足したものが、八苦です。4×8=32ある訳ではありません。
・生――生きることほど辛いものはありません。
・老――醜いものです。
・病――痛いです。
・死――恐いです。
・愛別離苦(あいべつりく)――愛するものとの別れは苦しいものです。
・怨憎会苦(おんぞうえく)――どうして怨み憎むものに会わなければならないのでしょうか。
・求不得苦(ぐふとくく)――どうして求めるものが得られないのでしょうか。
・五陰盛苦(ごおんじょうく)――物質と精神を構成する色・受・想・行・識という五つはどうして悪さをするのでしょうか。
五陰は五蘊(ごうん)とも言います。もう少し説明しますね。
・色――色彩ではなく、物質です。イコール肉体です。世界の構成要素です。
・受――受けて感じる、受け手の意見です。悟っていれば苦を受けても苦になりません。
・想――心にとめる想いのことです。実際に知覚したり、記憶の再生だったり、想像だったりします。
・行――意志や記憶です。苦行だけでは悟りを開くことはできません。
・識――認識です。意識のありようです。
この世の一切は、五蘊からできています。これらはすべて「ただある」だけです。心が揺れていれば、風が吹いているように感じます。逆に風が吹いていると感じていれば、心が揺れていることになります。
何もしなければ、何もしません。「ただある」――それだけです。
《色即是空/空即是色》
色即是空は、この世界の一切の色(物質)が、〈空(くう)〉だと述べています。空即是色は、〈空〉であるからこそ、この世界の一切は色(物質)だと述べています。
さて、〈空〉とは何でしょうか。
ここに、皿が一枚あるとしましょう。有田焼かしら? 李参平(りさんぺい)の作であれば、けっこうな値がします。
有田焼の李参平は、文禄の役(1592年―1593年)のときに渡来して、帰化して金ヶ江三兵衛となりました。ですから前は朝鮮半島の人です。
つまり、有田焼は朝鮮半島の文化が発祥です。けれど、今の朝鮮半島の文化が発祥ではありません。
文化というものは一度途絶えれば失われ、二度と再生することはありません。潰れたラーメン屋の跡地に、新しくできたラーメン屋が前と同じスープの味ならびっくりしますよ……。
さて、一枚の皿は、皿として使えます。多少割れても「金継ぎ(きんつぎ)」で、より美しくすることもできます。
しかし、どうでしょう。完全に割れて粉々になってしまったら? 元「皿」です。それはもはや皿とは言えません。ゴミです。
けれど、有田焼なら、その欠片を新しいものに混ぜて焼くこともできます。また、皿になるのです。
では、この皿はどこまでが皿で、どこからが皿ではないのでしょうか。
そこに皿としてとどめておくのは、私たちです。それらを解き放てばどうでしょうか?
粉々になった皿の破片を川に流してしまえば? 焼いて灰になってしまえば?
そこに縁起(因縁生起)――原因(因)や条件(縁)がなければ、どうでしょう?
皿は皿でなくなり、私たちも忘れてしまうでしょう。ふっと消えてしまうのです。
あまり「たとえ」としては相応しくないかもしれませんが……。
かつて、シッダルタ王子は「この世は苦に満ちている」と言った。釈迦は「この世は美しい」と言った。
【参考文献その他】
*中村元『龍樹』(講談社、2002年)
*大阪市立東洋陶磁美術館「安宅コレクション」
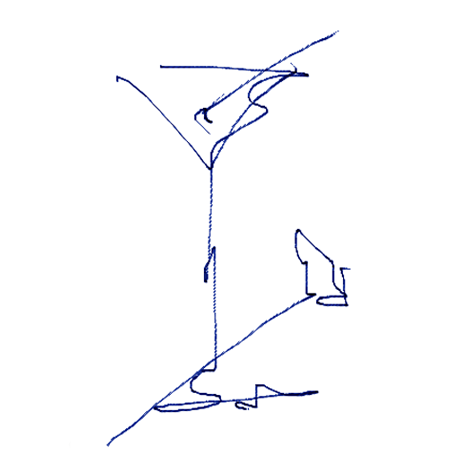




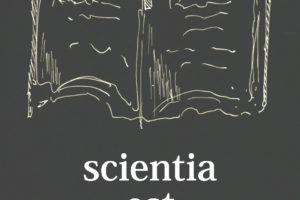


コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。