『恋は自死のようなもの』
“First love”
高校生の私は、親しい同性の友人から恋の相談を受けたが……。
※読切
※文庫本【10】頁(41文字17行)
※原稿用紙【10】枚(400字詰め)
【Caution!】
※この小説は虚構(フィクション)であり、実在の登場人物・組織・団体などとは一切関係ありません。
*****
――どうしようもない恋もあるのです。不可抗力の、とりとめもなく強い何らかの作用で、人は動かされます。それは別に異性だけではなく、同性に対しても物や事象に対しても起こりえます。
https://twitter.com/ichirikadomatsu/status/766059109879734272
いつになく深刻な顔をしていた。目の下に隈(くま)ができている。
「話があるんだ」
同じ高校の同級生には聞かれたくないらしい。校舎の陰で、周囲を気にしてから口を開いた。
「自殺ならやめたほうがいい。けっこう面倒だからな」
皮肉をこめて返した。内容を聞いてからでは遅い。
「もっとも自殺は止めようがないから、するなら俺の知らないところでやってくれ」
あの時の彼の目には私はどう映っていたのだろう。
「自殺?」
「自殺」
端的に答えた。
「いや違う違う。自殺じゃあない。恋愛の、そう恋の相談なんだ」
「同じようなものだろう。死に至る病(※)だ」
キェルケゴールだ。
助かれば麻疹(はしか)のようなものではある。
※デンマークの哲学者セーレン・キェルケゴール(Søren Kierkegaard、1813年5月5日―1855年11月11日)の書籍『死に至る病(Sygdommen til Døden)』(The Sickness Unto Death、1849年)から。死に至る病とは「絶望」のことで、『ヨハネによる福音書』第11章4節でイエス・キリストが友人ラザロを復活させたことにちなむ。
「俺じゃあなく、友だちの話なんだが――」
訂正が不十分だった。目が動揺している。本人だろう。
「道ならぬ恋なんだ」
「友だちが」
「友だちが」
他人の不幸は自分の幸福だ。
「不倫ならやめておけ。金がかかる」
面倒はゴメンだった。必ず助けるにしても。
「いや、特殊な話なんだ。それで告白しようかどうか悩んでいる。――友だちが」
バレバレだろう。
「やめておいたら?」
見下すような口調で返した。相手は私じゃないらしい。同性に告白されても困るが。
「どうして? きっと分かり合えると思うんだ」
「現実はそう甘くない。恋を伝えるのは、言葉で押し倒してるのと変わらないぜ」
眉間に皺(しわ)がよった。
「そこまで言うか? 相手も同じ気持ちなのに」
告白した後かよ。あっ違うか、一線を越えた後か。
「相手の気持ちなんて永遠に解るものか。幻想だ幻想」
「でも――」
「――誰にも迷惑がかからない恋なら、それは恋じゃないんだよ」
諦めたように俯きかげんの顔に言葉を続けた。
「自死はとめようがないからな」
「ジシ?」
「自ら死を――」
「――恋は自殺か……あはは笑えない」
笑えないのはこっちだ。
ただこの瞬間に、憂いをおびたこの親しい友人に私は恋してしまったのだから……。
後で聞くと、あの恋は終わったらしい。目が死んでいた。
その時に私が告白していればどうにかなったのかもしれない。
いやどうにもならなかったろう。そうしたものだ。
それからしばらくして、転校していった。
理由は父親の転勤だそうだ。
嘘だということが、私には分かった。
あの憂いの目をしていた。
大変なことになったのだろう。
話は聞いていない。誰も。
離れてからも、何度かメッセージをかわした。
当たり障りのない言葉が並んでいた。
私はラヴレターを書いて贈った。
返信はなかった。
卒業して大学、就職。
何人かの女性とつきあい、職場のマドンナと結婚した。
娘ができた。
そして、別れた。
私が好きになった同性は彼だけで、他には経験もなかった。
どうしようもない恋だったのだろう。
別に他の男性を好きになることもなかった。
だから、妻と別れたのは彼のせいじゃない。
娘とは幼いころに別れたきりで、会っていない。
結婚式には呼ばれないだろう。
呼ばれても行くことはないだろう。
今は別の女と住んでいる。
彼の話になったとき、理解のある女がある映画の話をした。
「まるで『ブロークバック・マウンテン』ね」
未見だった。
2005年の“Brokeback Mountain”の原作が書かれたのは1999年。
それ以前に似たような経験をしたのなら、知られていないだけで、よくある話なのだろう。
作中では、娘の結婚式に出る約束をした主人公が、永遠の愛を誓うのだという。
私には、その勇気はない。
【了】
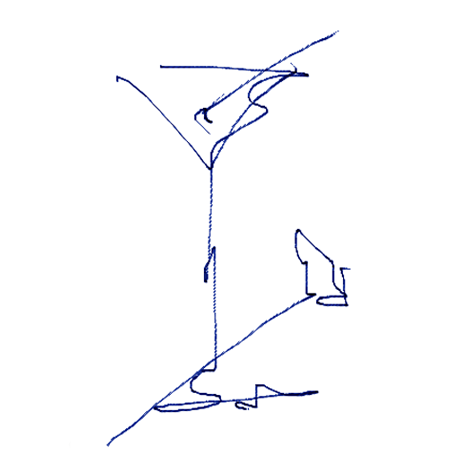
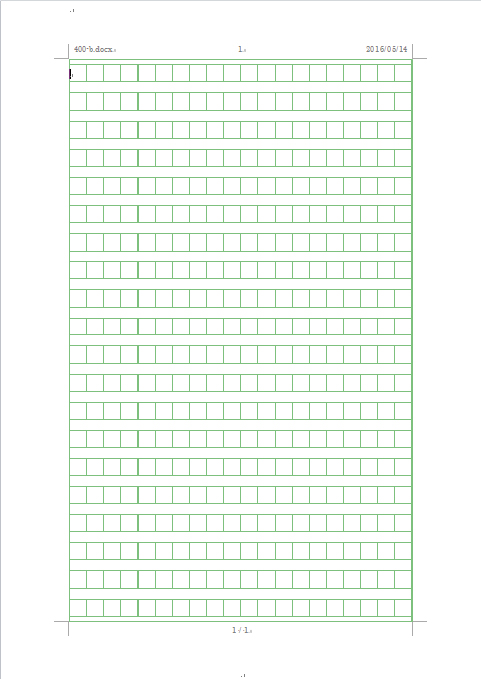


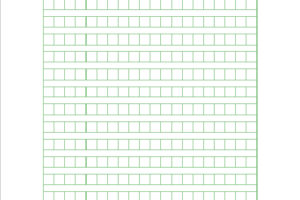


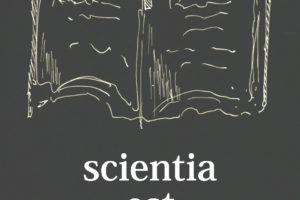


コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。