ブラック・ドッグ・デイズ「1.対価を得る(就業での罰金問題)」
“Black Dog Days”
君が思うほど、人の心は遠くない。――ただ、忘却は世の常だよ。
1.対価を得る(就業での罰金問題)
坂道を下る美少年の眼下に海が見えた。光の破片が南中した太陽から落ちている。垂水一樹(たるみいつき)が眩しさに右手を翳した。海岸が左にのびて大阪湾につづいていた。視線を戻し目を細めると、遠くに淡路島があった。
割れた器を繕うのに金継ぎがある。漆でつなぎ金をまとう。その景色は元よりも美しくあることが多い。
あの日、神戸に何があったか、レンガ造りのビル“ヂ”ングが物語っていた。
手にした携帯電話の住所と壁の住居表示を見比べていると、出前のカブが閉じられた正面玄関の前に止まった。笑顔で一瞥する出前の法被のくずし字は読めなかったが、岡持に〈さ倉〉とあった。蕎麦屋は身を屈み、横の潜戸の奥に消えていった。
慣れた出前と違い、華奢な少年はコサック・ダンスを踊れなかった。こけそうになって手にしていた封筒を落としてしまう。
拾いあげると、機械音が頭上から響いた。手動エレベータがゆっくりと下ってくる。籠の編目からの木漏れ日が、少年の頬にかかった。色が白い。
暗い玄関には、中央から天上に両翼を広げるような階段があった。両翼の上には一対のロダンのブロンズ像がある。
蕎麦屋は左の階段を登っていた。骨董品のエレベータを待っていては、それこそノビてしまうのだろう。
真似て少年も右の階段に足をかけた。二階を過ぎるときに、逡巡するエレベータと邂逅した。
濃紫のデザイナー・スーツを着たプラチナブロンドの美女だった。白手袋で眼鏡を正すと、ブルガリのバングルの音が響いた。その瞳は右がブラウン、左がグリーンのオッドアイだった。
何か見てはいけないものを見てしまったかのように、少年は立ちすくんでしまった。
視線も正面そのままに美女はまったく表情を変えなかった。地下まで下っていく様は、ギリシア神話の冥界の女王ペルセポネのようだった。
しばらく呆然としていたが、蕎麦屋の駆け下りる対岸の音に目を瞬(しばたた)かせた。四階を目指す。
古い扉を2回ノックした。返事がないので8桁の暗証番号を入力して開ける。けっこう重い。
正面に応接セットがあり、奥の机にPCモニタが4面も置かれていた。
後ろでオートロックの音がした。ビルは古いが事務所としての設備はあるらしい。
右手前が化粧室で、並びにキッチンがあった。左奥に扉があり、物音がした。
2回ノックした。
「はい……」
若い女性の声だった。少年は躊躇わず扉を開いた。――それがいけなかった。
長い髪の美しい女と目があった。
「!」
畳の上で二つの乳房がゆれていた。円を描いていたピンク色の乳首が止まった次の瞬間、女が目を閉じて、男の上に重なった。
「はい?」
寝ていたハンサムが、首をずらして左の目だけで少年を見た。
「えっ? あのこれは……」
目を開いたままの少年はそう答えるしかなかった。
「女の裸ぐらい見たことあるだろう?」
そう言うと、やさしく女を横に転がした。高級そうな細身の金縁の眼鏡をかける。
「きゃはは」
美女が身体を上げながら笑った。Cカップの胸がゆれる。
「恥じらいってものがないのか、着れ(原文ママ)、まりも」
バスタオルを掴んだまりもが口に人差指をあてながら裸足で、少年の横を通り過ぎていった。
「……長藻(ながも)さん、ですか?」
気を取り直した少年が聞いた。
「自分の名前を先に言え。月乃(つきの)さんに教わらなかったのか?」
「……垂水一樹(たるみいつき)です。月姉(つきねえ)に言われて――いえ、あの、叔母の月乃から長藻さんに相談するようにと言われたので、お伺いしました」
「月姉か……」
長藻秋詠(ながもときなが)が、きれいに畳まれた麻のシャツに袖をとおしながら苦笑した。
「保護者の自覚があるのか、あいつ」
「秋詠(あきえい)さん、例の件よろちくび♩」
いつの間にか着替えたまりもが声をかけた。濃緑のブラウスに、淡いベージュのコットンパンツ、アシックスのブルーのシューズ。首には、シューズと同じ色柄のエルメスのスカーフをしている。
「あいよ」
声を聞いて安心したまりもが、一樹の耳に顔をやった。
「言ったら殺すわよ」
囁いて念を押した。黙ってうなずくしかない。モンベルのバックパックを片掛けに嵐のように消えていった。
「何か弱みでもあるのか?」
ブラウンのウールのスラックスに下駄を履いた秋詠が、応接に手をやった。
「いえ、そういう訳じゃあないですけど」
「ん? 違う。――仕事の話。何?」
一樹が封筒から、給与明細を出した。西宮のスーパーマーケットの名がある。
手に取ろうとした秋詠が指を止め、テーブル横にあるウェット・ティッシュで指をきれいにした。
「何だこれは?」
「給与明細です」
「フフフ。見たら解るよ。わたしが聞いているのは、状況であって、状態じゃない」
「えっ?」
「分からないか。結論から言うからな。いつも齟齬をきたす。雪乃(ゆきの)がいれば、説明してくれるものを……」
「母をご存知なんですか?」
上目づかいに一樹が聞いた。
「知っているも何も……。すう……確かに似ている」
秋詠が言葉を切って、再度つづけた。
「5分遅刻で0・5時間カットだと? 1時間遅刻したら1日パアだな。それでか」
明細を投げた。一樹が正面に見えるように落ちる。
「何がです?」
「15時の予定が、この時間になったのは。この分だと、入れていたシフトを休むときは誰かを入れないと罰金なのだろう……」
秋詠が一樹の瞳を見た。
「アルバイトの先輩の替わり……女性……若い。とすると、今日はヒマかと聞かれて、鼻の下をのばしてヒマだと答えたら、デートなので替わってほしいと言われたという訳か」
「どっどうしてそれを!」
動揺する一樹に、秋詠が冷たい視線を返した。
「いつものパターンだよ」
4回ノックがした。
「どうぞ」
「お待たせ♩」
ティファニーのプラチナのチョーカーとピアスをした美女が岡持を手にしていた。香港のデザイナー黄琳玲(こうりんれい)のダークスーツの着こなしが優雅な大人の女だった。
「ん? お客さま?」
そういう赤木南々子(あかぎななこ)の目に、奥の乱れた布団が映った。
「秋詠(あきえい)さんとうとう少年までその毒牙に……」
「違う、違う南々子」
「黙っておいてあげるわ……。あなたが犯罪者になるなんて忍びないもの」
南々子が片手を背にまわした。
「通報は止(や)めろ。この子は雪乃の――」
秋詠が南々子の携帯をとりあげて、テーブルに置いた。
「――昔の恋人の忘れ形見に手を付けるの?」
「お前絶対勘違いしている」
「ふう……先に食べましょう。――あなたお名前は? 私南々子。南々子さんと呼んでくれると嬉しい」
「南々子お姉さん? 僕は垂水一樹です」
「あっそれいいかも。よろしくお願い。……ん」
岡持から三枚の蕎麦を出す南々子が、明細に目を止めた。
「違法じゃあない?」
「だからその件で……」
「食べるわよね? 美味しいわよ。ああ遠慮しないの。アレルギーじゃあないんでしょう?」
秋詠の分はないらしい。
「ええ」
「じゃあやっちゃって。――はい、いただきまーす」
聞いていない南々子は割箸を横に、右手を奥、左手を手前にして割った。
「いいんですか?」
秋詠に聞く一樹だった。
「どうぞ。どうせ二日酔いだし……」
「じゃあ遠慮なく」
一樹が割り箸を縦にして、割った。
「――シャワーしてくる。その間に躾けておいてくれ」
憂鬱な顔をした秋詠が化粧室の奥のバスルームに消えた。
「はーい」
トーンの落ちた声で、南々子が答えた。
「シツケって何をです?」
「食事のマナーよ。お箸はこうやって横に持って、両手で割るの」
「はあ……」
「『躾』って漢字書ける?」
「シツケですか? ?」
「『その身が美しい』と書くのよ。――はい、お箸を持って。あっその前に『いただきます』して」
「いただきます」
一樹が両手を合わせた。
「お箸は持てるみたいだけど、持つ前の段階が……こう右手で持って左手で添えて、もう一度右手。そうそうそんな感じ。持ち方はいいかしら……あーそんなに蕎麦を上にあげちゃダメ。顔を出しちゃダメ。それ犬食い。はいOK。二枚とも食べていいわよ。秋詠さんの分だから」
「……はい」
「口の中に入っているときは喋っちゃダメ」
「うくうく……すみません」
「いいのいいの。直せばいいんだから。でしょ、秋詠さん?」
「そういうこと。箸を持ちながら振り返るな」
洗い髪をタオルでまとめた秋詠が答えた。チャコールグレイのスーツはテーラーの三つ揃えらしく、襟のあるウェストコートに袖をとおした。
南々子のテヘペロ。笑窪が愛らしい。
*****
赤木南々子が岡持を手にして帰ると、ネクタイをした長藻秋詠がMacBookに数値を入れた。本来であれば支払われたであろう正規の金額が表示される。
「どうする?」
「と、言いますと?」
秋詠の質問に一樹が答えた。
「一つは『諦める』というのがある。そうした人に出会ってしまった自分の不幸を嘆く」
「それは……叔母にも言われました。『騙されたヤツが悪いのよ』って……。でも、正直者がバカを見る世界っておかしいじゃあないですか?」
「別におかしくはないだろう」
真顔で秋詠が返した。
「善人は早く死ぬ」
「そんな……そんな世界おかしいでしょう!」
「生きている人は全員悪人なのだよ」
「長藻さんは自分のことを自分で悪人だと言うんですか?」
「悪人だよ。死んだら善人になるのだ。日本ではね」
「ふう……」
目を伏せる一樹だった。見ても明細の数値は変わらない。
「ただね、悪には悪のルールがある。それと、単なる悪――バッドだけではなくて、邪悪――イービルがある。これは違う。そんな顔をするな。自分が善人だと思うのか?」
「少なくともそう思っています。そう思いたいです」
「善にも二つある。グッドとホーリーだ。ホーリーは聖だな。君はどちらだ?」
「……ホーリーではないことは確かです。でもそう言われるとグッドとも言えないです。その中間のセンターよりややグッド寄りでありたい――」
「人生そうそう巧くいく訳ないだろう? そのセンターのニュートラル状態を『中庸』という。アリストテレスも言っているが、儒教では四書の一つでもある。考えてみろよ。きちんと毎回毎回センターにいる、バランスが取れている、そうした人生がどれだけある? ないよ。ないのだ。悪を自覚して善を行え」
「……偽善者でいろと? そう言うんですか?」
「自分で選べ。君の人生だ」
「失礼しました」
怒った一樹が明細をしわくちゃに掴むと席を立った。南々子の携帯電話が忘れられている。
「座れ」
長藻秋詠の威圧感に、垂水一樹が一歩も動けなかった。
「いいから座れ」
顔を斜めに伏せた。
「今日から三日間、月乃さんがいない。わたしが保護者だ。君は子供で、選択権はない」
「そんな無茶苦茶な!」
「短気を起こすな」
「怒らせているのはあなたでしょう!?」
「子供が真剣に話しているのだろう? わたしも真剣に話をしている」
「どこがですか! 自分の言いたいことしか言っていないじゃあないですか! そりゃ僕は騙されましたよ。でも先輩もみんなも一生懸命働いているんですよ? 僕だけが文句を言って辞めればそれでいいんですか?」
「他人なんて知らない」
「ふざけないでください!」
「どちらか一人を助けなければならない時、君なら月乃さんとわたしのどちらを助ける?」
秋詠が膝上に肘を乗せ、指を組んだ。ウェストコートから灰色のサスペンダー(ブレイシーズ)がのぞいている。
「そんなの月姉に決まってるじゃあないですか!」
「そうやって君の母親は、自分の生命を代償に君を助けたのだ。あの日」
組んだ小指を立てて、一樹を差した。
「ふっふっ……」
緊張の糸が切れたのだろう、一樹の頬に涙が伝わった。
「母はどんな死に様だったんですか? 誰も教えてくれません……」
秋詠がハンカチを手渡した。
「本人に聞け」
両手を広げ、天井に向けた。
「聞けませんやん……」
「死に様は一瞬。生き方の切り口でしかない。――話を続けていいかしら?」
「どうぞ……」
やる気のない声がした。
「もう一つは『逃げる』だな。これも却下と。後は『戦う』」
「戦う? 何を戦うんですか?」
「『権利のための闘争』だよ。ルドルフ・フォン・イェーリング曰く『自己の正当な権利を主張すること』だ」
cf.
イェーリング、村上淳一訳『権利のための闘争』(岩波書店、1982年)P48
「言って払ってくれるんなら、名鳥羽(なとば)さんが文句言ったときに払ってくれましたよ」
「どなた?」
「あっごめんなさい。パートのおばちゃんです」
「主婦?」
「はい」
「子供がいたら、遅刻もするでしょうに」
「いえ。子供はいません。単にだらしないだけだと思います」
「15の子に言われる大人もやるせないな。……きちんと請求するだけだよ」
「どうやって払ってもらうんです?」
「『払ってくれなければ、訴えます』で問題ないでしょう」
「そんな大げさな……」
「フフフ。もう大げさになっている。最低賃金割っているし、罰金も行き過ぎだし、不当だろう」
「でもみんなに迷惑がかかるじゃあないですか……」
「そのみんなにわたし、入っている?」
秋詠が首をかしげた。一樹は壺に入ったらしい。笑いをこらえている。
「なんとか穏便になりませんか?」
「相手の出方次第だろう。暴行事件になりそう?」
「いえ。社長の奥さんはケンカっ早いですけど、怒鳴るだけで、手は上げません」
「物壊したりとかは?」
「投げつけたりはしています。スーツで行ったら汚されるかも……」
「新品になるな」
ウェストコートの襟に視線を向けた。
「そっちですか」
「物事は前向きに考えないと」
「悪人ですね」
「そう言ったけれど。さて、戦うにしても確認しておきたいことがある」
「はい?」
「覚悟だ」
「覚悟。戦う覚悟ならできています。最後まで戦います」
「いや違う。最悪の覚悟だ。『口論から殺される』かもしれないし、君も『反撃して殺人者になる』かもしれない」
「そんなことになる訳ないじゃあないですか」
「でも想像したか?」
「な、り、ま、せ、ん」
「では、『スーパーが潰れる』とかは?『社長やその妻に恨まれて刺される』とかは? 潰れる前でも、『給与が支払われなくなって他の従業員から恨まれる』とかは?」
「そんな……」
「確かに言う通り君は善人かもしれない。でもね。世の中『最悪の想像ができる』ことが大切なのだよ。善人はそれができない。できても『未必の故意』にもなる」
「『未必の故意』ってなんですか?」
「常識だ。自分で調べてくれ。とりあえず書類を作って、二人で行こうか」
「後でお願いできますか? 京町堀川(きょうまちぼりがわ)先輩のシフト確認したら、僕より早いので先に行かなくちゃいけないんです」
「モメたら、途中退場だぞ?」
「それは困ります。せっかくシフトを替わったのに、京町堀川先輩に迷惑がかかってしまうじゃあないですか!」
「どうしてその迷惑にわたしが入っていない?」
「あ!」
「あ、じゃない」
*****
神戸地方法務局に出向いた長藻秋詠が、赤木南々子のホンダS2000を見つけた。流石に目立つ。
履歴事項全部証明書に記入していると、膝カックンされた。
「ふっふー」
笑顔の南々子だった。キュート。
「はいよ」
ウェストコートのポケットから携帯電話を出して渡した。
「あっやっぱり? サンキュー」
着信を調べてなおした。
「やっぱり行くの?」
「雪乃の忘れ形見だからな……」
「秋詠(あきえい)さんの子じゃないの?」
南々子が斜め上を見た。
「ここだけの話、雪乃は宇宙人なのだ」
「何それ笑う」
笑顔がチャーミングだ。
「内緒だぞ」
「はいーはい。じゃあね。――あっ今晩来るの?」
「いや、たぶん大変なことになるだろう」
「刺されないようにね」
手をピストルの形にして、笑いながら消えていった。
*****
西宮にあるそのスーパーマーケットに到着したときは、繁忙時刻の前だった。
法務局から前もって電話を入れている長藻秋詠は、社長の軽いあしらいを受けることになった。
奥の事務所には、副社長である妻が銜え煙草で革の椅子に座って計算をしていた。秋詠が名前を名乗っても煙草を消すこともしなかった。
破れたパイプ椅子を案内されるが、立ったまま白手袋の秋詠がアタッシェケースからAdobe Illustratorで作られた書類を出して、机の上に置いた。
小塚フォントのレイアウトが美しい。内容は言うまでもなく、正規の金額の支払要求だった。
「あなた誰?」
高圧的な妻に、あわれむような秋詠が口を開いた。
「垂水一樹の保護者です」
「ふっ何それ。イッキーとどういう関係なの? あなたが父親なの? あの父無し子(ててなしご)が」
秋詠が指を鳴らした。
「最初に申し上げておきますが、法的におかしいことがあれば、法に訴えます」
「だからあんた誰よ! 弁護士?」
煙草を灰皿に突っ込んで揉みくちゃにした。
「いいえ、垂水一樹の保護者です」
「だ、か、ら、関係ないんだったら放っといてよ。身内なら証拠見せなさいよ」
「あなたは自分の子が危険な状態になったときに、いちいち住民票の写しを用意するのですか?」
「フン! 何が危険なのよ?」
「法に反している――十分危険ですが」
「それはあの子が遅刻するからでしょう? 何もやりたくてやっている訳じゃあなし。きちんと働いてくれたらきちんと支払うわよ」
秋詠がアタッシェからツバメノートを出した。胸の内ポケットからペリカンの万年筆を出す。
「記録してもよろしいですか?」
「どうぞ」
「『きちんと払う』と」
「きちんとね」
「わたくしは別に、他の従業員のことは問題にしていません。ただ、垂水一樹の給与を正当にお支払いしていただけたら帰ります」
「人の話聞いてる? 遅刻したから引いたのよ。きちんと働いてくれたら、は、ら、うって言ってるの!」
「幾ら引いたのですか?」
「書いてあるじゃあない」
「『3回遅刻で合計2時間分を罰則として4月分の給与から引いた』でよろしいですか、副社長?」
秋詠が万年筆で書いている。
「そうよ。一分一秒でも遅刻は遅刻。罰金です」
秋詠が内ポケットから、ICレコーダを出した。
“「『3回遅刻で合計2時間分を罰則として4月分の給与から引いた』でよろしいですか、副社長?」……「そうよ。一分一秒でも遅刻は遅刻。罰金です」”
「ちょっとあんた何してんのよ!」
「記録してよいと許可をもらっていますが? 何か?」
「貸しなさいよ。何してんのよ。コレどうやって消すのよ」
妻がひったくって、データを消した。
「おいおい!」
社長が声を上げた。
「騙し討ちしたのはコイツでしょ? 関係ないわよ。はい」
「証拠を消しましたね?」
返されたICレコーダを机に置いて聞いた。
「消したわよ。証拠隠滅! もういいから帰りなさいよ。こっちも忙しいんだから」
秋詠が内ポケットから、もう一台ICレコーダを出した。
「あんた何考えてんのよ!」
今度は掴めない。秋詠が、猫をじゃらしているようにしか見えない。
「一つあるものは二つある。――完全に悪質ですね。こちらとしては穏便に処理したいだけなのですがご希望とあれば、労働基準監督署ではなく裁判所に行ってもよろしいのですが」
「それはちょっと」
社長が両手を差し出して言った。
「はっ! 訴える気? 裁判に幾ら経かると思ってるのよ? できっこないわよ。こんな端金で! ――それより貸しなさいよ。消すから」
妻の言葉に、秋詠がやわらかく微笑んだ。妻の目が凍った。
「どうやら帳簿がもう一冊あるように見えるのですが……どうでしょう?」
妻がPCのモニタを見やった。
「裁判所ではなく税務署のほうがよろしいでしょうか?」
「そっそれは困る! 頼む。――もう払え。払ってしまえ」
「えーでも」
「ちょっとやないか!」
ぶつぶつ言いながら、妻が引き出しを開いた。紙幣と硬貨を机に並べた。
「ほんとに訴えないんでしょうね?」
冷静になった妻が聞いた。
「そのデータ、消してくれる?」
ノートをアタッシェに入れ、対価に手をやった秋詠の手を、妻がしっかり掴んだ。秋詠の鋭い視線に妻が手を放した。手にしたICレコーダのデータを消去して、数値がゼロになった状態を見せた。
アタッシェに二台のICレコーダとノートを入れ、秋詠がジップロックと領収証を出した。
対価をジップロックに入れ、アタッシェに放り込んだ。領収証を置く。
「さて、もう一つ」
「はい?」
終わったと思った妻の声が上擦った。
「このような『悪意』のある可能性の場所にあっては『あとあと問題になる』可能があります。よって、今すぐ辞めさせたいので、本日現時刻までで精算していただけますか?」
「なんですって! 今働いてるのよ?」
「あまりにあまりだろう。どうせ後で同じだけ、いや確実にそれ以上、悪意を返す――意趣返しをするのだろう? そうしてきたのだろう? そうやって生きていくのだろう?」
やわらかな笑顔。静かな口調の長藻秋詠だった。その瞳の奥に闇があった。
「……」
声にならない妻が握りしめた片手を上げた。わなわなと震えている。
「当たり前ですが、暴行があれば通報します」
「おい、よせ!」
「賢明ですね。刑法第208条を言いましょうか?」
cf.
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「結構です!」
社長から渡されたタイムカードを見て、妻がデータを入力していった。
「まさかそういうことはないと思いますが、源泉所得税――」
「――分かってるわよ!」
キーボードが壊れないのが不思議だった。
*****
三人ほど客が並んでいる垂水一樹のレジに、社長と妻が来た。長藻秋詠がつづく。
「帰んなさい。イッキー」
「えっでも」
「馘よ。馘。帰りなさいって言ってるのよ!」
「僕は京町堀川先輩の替わりなんで――」
「――帰れって! あんたなんていなくなればいいのよ。ハッ!」
「でもレジ……どうするんですか?」
「あたしが打つわ。どいて。――いらっしゃいませ」
どかせると、抑揚のない声で困惑している年配の女性客に挨拶した。手慣れているらしくバーコードを認識する音がつづいた。
「一度レジを締めていただけますか? 後で足りないとか言われるのも問題ですし」
長藻秋詠が首を斜めにして言った。
「そんなことしないわよ!」
妻が振り返り怒鳴った。涙目になっている。他のレジを担当していたパートの名鳥羽や大学生のアルバイトの鴬鳥良(うぐいすよし)、中卒でパートの小山田由子(おやまだゆうこ)も思わず手を止めて振り返ってしまう。
「では言質をいただきましたので、これで失礼します」
秋詠が内ポケットから、三台目のICレコーダを出して録音を止めた。
「二つあるものは三つある」
秋詠から荷物を渡された一樹が店から出て振り返ると、社長の妻がレジでうずくまっているのが見えた。
「なんて事してくれたんです!」
「迷惑になる。場所変えよう」
「納得できません!」
「これでも平和的に解決したほうだよ。事件・事故は起こらなかった。――とりあえず場所を変えよう。迷惑になる」
「説明してください」
「来い」
「嫌です」
レジ袋を持ったさきほどの女性客が、一樹を見て怪訝な顔をしている。振り返ると、妻が無表情にレジをこなしていた。
「納得してませんからね」
しぶしぶ一樹が秋詠に従った。
「フフフ。納得して生きている人なんていないよ。――“God’s in his heaven― All’s right with the world! ”」
*****
焼鳥のチェーン店の暖簾を二人がくぐった。
「いらっしゃい!」
手前の席で大学生が騒がしく宴会をしていて、若く美しい女性がトイレに行くと言ってフラフラと立った。
奥の席から手が上がる。ソバージュの長身の美女だった。長藻秋詠が軽く手を上げた。ハンサムな秋詠らしく、その手で倒れそうになる女性を支えた。
あまりに自然で「ありがとうございます」と素直に言えた女性だが、後ろの垂水一樹を見た次の瞬間、一樹の頬を平手打ちした。
「あんたなんでこんなとこにいるのよ!」
一樹の先輩の京町堀川文(きょうまちぼりがわあや)だった。
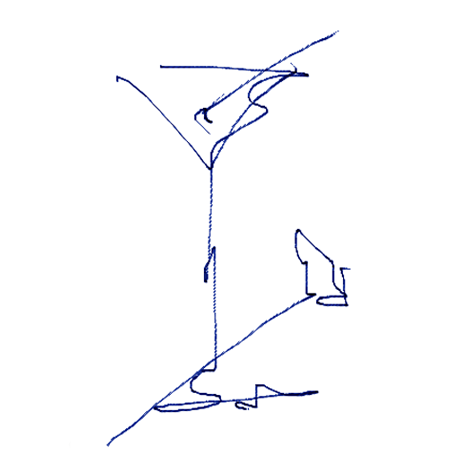
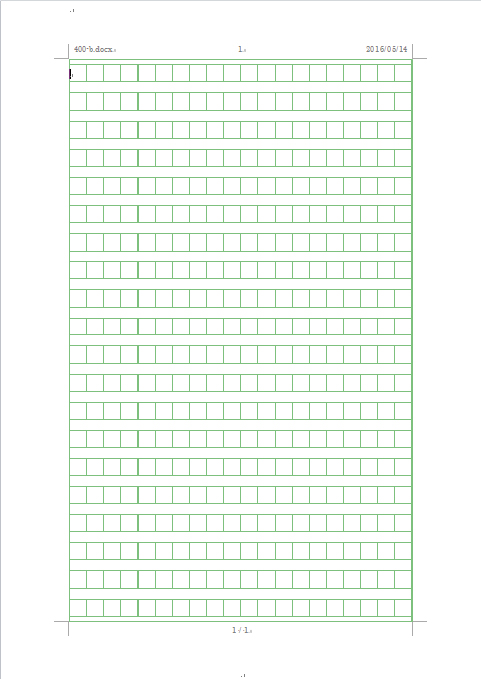


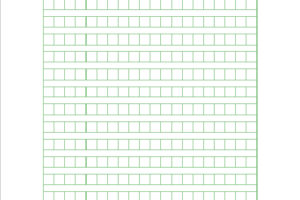


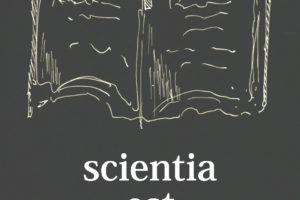


コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。