『黒塚』小説
“kurozuka”
六分桜の下には死体が埋まっていた。それを知らぬはずのない長藻秋詠が、残り梅の香り漂う道を歩いていた。英字新聞に白い菊が一輪つつまれている。春日なのに暑い。陽の光が金縁の眼鏡に菱形に映しだされる。ゆっくりと目を瞑り、それでも歩みを止めずゆっくりと開いた。墓石が永遠に続くように並んでいた。
新聞を広げいっしょに巻いていた線香を横におくと、命日らしく午前に参った客の白菊の束の横に添えた。人とは関わらずそれでいて礼儀を忘れない長藻秋詠らしい。手桶の水をかけると熱い石から湯気がでた。もはや灰になっているとはいえ、死者もそこにあるのは嫌なのだろう。
マッチで新聞に火をつけ、線香にうつし、すっと手をやると火が消え煙がたった。線香を半分に取り分け横においた。合掌。
視線を感じた長藻秋詠が振り返ると、薄墨の和服の美女がそこにいた。帯締めの緋色がいじらしい。
「過人を覚えていてくださるのはあなただけですわ」
解れ髪(ほつれがみ)を左薬指で耳に流した。艶。
「人はいずれ消えます」
とはいえ線香が消えるまでまだ間がある。
「お茶などいかがかしら?」
首をかしげた。
「いただきましょう」
その前にと、長藻秋詠は六地蔵にまいったあとで、無縁仏に残りの線香をそなえ手をあわせた。雨風(あめかぜ)がうがった石は砂に変わろうとしていた。石の刻と人の時は違う。
寺の庭に緋毛氈(ひもうせん)がしかれていた。野点(のだて)だ。さりとて傘下に風炉はなく魔法瓶のお湯を使っていた。
御点前。他に客はいない。
簡単だが、礼にかなった茶を愉しんだ。金継(きんつ)ぎの油滴天目(ゆてきてんもく)茶碗が美しい。
「十三回忌でした」
数字にあまい長藻秋詠のために女性が伝えた。
「もうそんなになりますか……」
割れた箇所を継いだ金をなでた。今年で12年だった。一周忌の翌年が三回忌で一つ多く数えるからちょうど十二支が一周する。
「海を渡ろうかと思いますの……」
伏し目がちに言う言葉には、もう二度と帰ってこないことを含んでいた。
「それもいいかもしれません。……さみしくなりますが」
「感謝しておりますのよ。わたくし……」
言い訳ではない言い訳だった。そのどうしようもないことが何か長藻秋詠は聞かなかった。
「お子さんたちは知っているのですか?」
「くだんの件はあの子たちには伝えておりませんの。不幸を伝えずとも辛酸をなめたことは忘れないでしょう。ただ、一人、あなただけを悪者にしてしまいました」
長藻秋詠が目を細め、微笑んだ。
「慣れていますよ」
桜の遠くに雨雲が見える。
「……墓所も売ってあの子たちの足しにしようかと思っています」
「差し出がましいようですが、多少でしたらご用意しますよ」
「いえ、お申し出だけで十分です。足らずがわたくしの為人(ひととなり)なのでしょう」
「さみしくなります」
長藻秋詠がもう一度だけ言うと、女性がもう一服すすめた。それ以上は言葉をかわさず、その時間を楽しんだ。
女性の見送りに「また会いましょう」と言う長藻秋詠だったが、それが本当の「さようなら」だった。
桜を揺らす雨風が吹くと、本堂が消えていた。焼け跡に長藻秋詠が一人立っていた。足下に油滴天目の欠片があったが、手をのばす前に雨に溶け土に還ってしまう。もはや継ぎはできない。
「黒塚(くろづか)……」
無表情に雨の寺を後にすると、墓石が次々と石片に変わっていった。
山門に戻るころには、梅の香りも桜の色も消えていた。あるのはただの廃寺だった。
【参考文献その他】
*能「黒塚」
*月岡芳年『奥州安達がはらひとつ家の図』
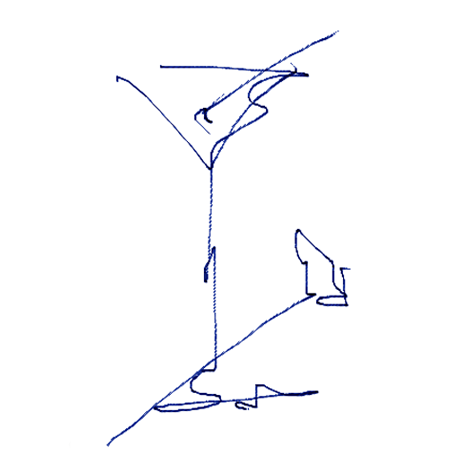
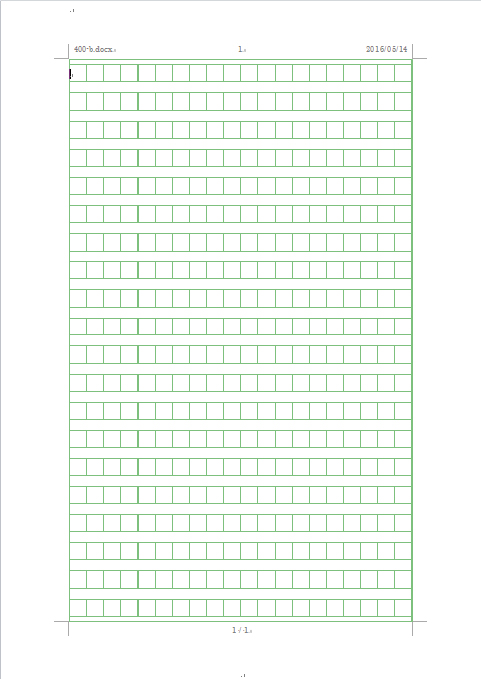


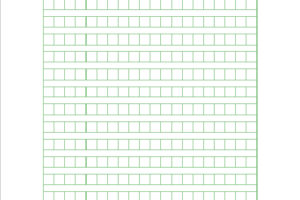


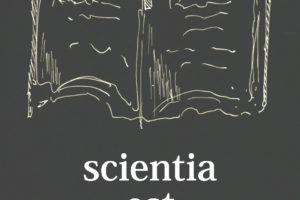


コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。