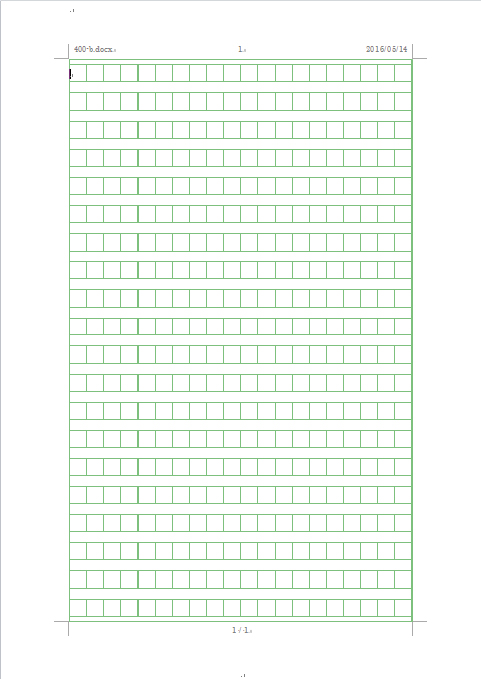『どうしてぼくは事象の地平面にいるのだろうか』
〝Beyond The Event Horizon〟——事象の地平面の彼方(かなた)
0.原風景
力なく夕闇に立つ少年が、原風景だ。憂いの瞳と、和らいだ笑み。
*****
1.美少年来訪
夜雪、時の流れの分水界(ぶんすいかい)にある老賢者の屋敷前に美少年が捨て置かれた。
美麗な紳士(ハンサム)が左手で指折り数えた。金縁眼鏡をただす。
「悪く思うなよ」
冷たくなった少年の懐から金貨を失敬すると雪風に消えた。
*****
話し終えた少年が白湯(さゆ)を口にした。やわらかな温かみらしく喉をうるおしていく。
水面(みなも)の緑髪の美少年の顔はやや幼かった。さきほどまで冷たくゆれていた丸天井のランプが静かに光っている。壁一面に書物があり、いつの時代かわからない機材が雑多に置かれていた。
円テーブルの左に座っていた老賢者が眼鏡をただすと、女執事が指をすっと動かした。巨乳が微妙にうごく。
飲み終えたカップの湯量が自然と増した。魔法ではなく技術なのだが、少年には解らない。アーサー・C・クラーク。
湯気がたつほど十分に熱い。三献茶。
「そこからは記憶が曖昧(あいまい)で、気づくとこちらにご厄介になっていたんです。本当に、本当にありがとうございました」
言葉がより明瞭になった。やわらかな笑顔。毛布にくるまれた少年が足湯につかった指先を動かした。どうにか感覚はもどったらしい。
二重窓の外の雪はしずしずとあるばかり。まばたきを何度かした。生きているのが不思議なのだろう。
老賢者が少年の肩に手をやっていたわると、ずれた毛布をかけなおした。ゆっくり立ち上がる。女執事が音もなくテーブルをどかすと、老賢者みずから少年の足をふいてあげるのだった。
「ちょっ、ちょっと困ります。自分でできますから」
「こうしたときは甘えるものじゃよ」
指の間もていねいに拭き取ると、かるく手をかざした。次の右足も同様に。うっすらと少年の頬に紅がもどった。朝の紅顔。
くったくがないというのは美少年の笑い声をいうのだろう。何か見つけると興味深く慎重に考察しては質問をくりかえし、老賢者をあきさせなかった。
「どれ、すこし〝みて〟みよう」
老賢者が少年の頭に手をかざした。
切り取られた記憶の修復を試みたが、きれいになくなっていた。強引につなぎあわせることもできるが、それでは少年の人生に負荷を及ぼしてしまう。
洗濯した私服を着ると、童顔でも年相応に見えなくもない。レッドブラウンの革靴に、ベージュのコットンパンツ、ライトブラウンの麻混のジャケット、ライトブルーのシャツ、それにベビィブルーのポケットチーフ。
——美少年で令子息……。
女執事が推察するに、食事前に両手をあわせて「いただきます」というからには日本人なのだろう。それもいいところの。
——それがどうして? 雪夜に捨て置かれることになったのかしら。
女執事の脳裏に疑問符があるのは否めない。いつまでも見ていたいが、そうも言っていられなかった。
「記憶がなくても特に不便はありませんから。老賢者さま。本当にお世話になりました」
ていねいに深く礼をした。
「ただの爺(じじい)じゃよ」
「ほんとうに神さまではないのですか? こちらが死後の世界ではなくて?」
「あなたがいた時空の思考からすると事象の地平面にちかいですね。もっともブラックジョークですが」
毛布を折り目にそって折りながら、アルトの美声が辛辣に告げた。なお、人間が事象の地平面の彼方(かなた)を知ることはない。絶対に。
「異世界といったほうが無難じゃろうな」
「似て非なるものですが……」
女執事ははやく追い出したいらしい。
「ここから出るのは一方通行でのお……。困難も多い……。さりとて、ずっといれば存在が消えてしまうのじゃよ」
難しい専門用語を使わず老賢者が説明した。
「この地所は、時の流れの分水界(ぶんすいかい)なのです。時を水とするならば、時がここから分かれ流れる境界にあたります。不安分子をここにとどまらせておくのは危険なのです。砂時計に異物があれば時が止まってしまうように」
女執事には、何が起こるか判断できなかった。だが、それはいつも最悪の形であらわれる。
——きっと女執事さんが……。
少年が時と戦う女執事を想像したが、どうやって存在が消えてしまうのかを聞くほど愚かではなかった。
とはいえ、である。行き倒れの少年は一文無しであり、直近の出来事と記憶をなくしていた。その名さえも。
「今日は何の日じゃったかな」
「灰の水曜日です」
「なある。では名を灰(アッシュ)としよう。いかがかな」
あまりよい名とはいえないが、断る理由もなかった。それに少年自身あまり宗教を気にしていないらしい。日本人だからだろう。
「はい。よろしくお願いします」
そう言うなりアッシュの緑髪が長くなりグレイに染まっていった。名は体を表す——そうした術(すべ)が老賢者にあった。
与えられたのは名前の他に金貨を十袋。腰が重い。金の比重は水の一九・三倍ほどある。缶珈琲一本分の量だとしても、二五〇ミリリットルで四八二五グラム——つまり約四・八キログラムもある。五千円/グラムとすると、二四〇〇万円ほどか。路銀には多すぎるが、それだけ危険だとも言えた。
「エルゴの教会で祈り人(いのりびと)のプレイアにねがえば、出口まで無事に案内してくれるじゃろう」
「〝Prayer〟です。〝Player〟ではなく、PRプレイア」
女執事も案外優しいのかもしれない。日本人にLRは理解しにくい。
「では、エルゴの境界線まで送ります」
「はい」
言うが早いか着いていた。眩しい。手をかざすと、遠くに高い塀が見えた。エルゴの街だろう。
あたりを見回すと草原が海のように広がっていた。小高い山や川もあり、目をこらすと黒い森があった。とても地獄には思えないが、地獄はどこにでもある。
ともあれアッシュは街まで歩くことにした。さいわい幅広の道は煉瓦(れんが)で舗装されており、歩くのに難はなかった。
——あの雪の夜、ぼくを背負ってきてくれた紳士は誰なんだろう……。
少年の身分を証明するものは一切なかった。薬指でグレイの解れ髪(ほつれがみ)を耳にまとめた。
——泥棒さんだけれど、たぶん……だけれど、あの人はぼくを老賢者さまのところまで運んでくれたんだ。でも、どうして一緒に中に入らなかったんだろう……。あの寒さのなか、何に追われていたんだろう……。えっ、何かに追われていた?
背後から馬車の音が聞こえた。金属音も多い。
振り返ると、空想中世小説のような荘厳な軍隊だった。縦一列で五六台はあるだろうか。露払いの兵士が旗をあげていた。四分割された紋章の二つはドラゴンとそれを貫く剣(つるぎ)の意匠(デザイン)だった。もう二つはクロスした線だけが書かれていた。
——王族か貴族? それにあのクロスは……。
見とれている間に近づいてきた。日本の大名行列なら土下座だが、中世風の異世界でそれはないだろう。とりあえずアッシュは道をはずれ、砂利の上に立つことにした。心なしか頭(こうべ)をたれた。
二台が行き過ぎると、音もなくすべてが停車した。見上げると、一列に並んでいた。歩兵が微動だにしていない。よく訓練されている。
「えっ?」
正面の馬車の扉が開き女官につづいて、しずしずと幼い淑女(レディ)が降りてきた。シルバーブロンド。
——きれい。
まばたきした。
「アッシュさまでございますね?」
二名いる女官の一人が声をかけた。
「はいそうです」
にこやかに答えると、淑女(レディ)が前にでた。息を深くすう。
「我が名はセジール・フォン・ウァレンス。ウァレン辺境伯第三女にして王位継承権三一位——」
二分は話していた。ピカソ。
息継ぎせずに言ったセジールがぜいぜいしていた。女官が二人とも背中をさすっている。身分の高い人は大変である。
「わたくしの名はアッシュです。こちらの国ははじめてでして、敬称は何と申し上げたらよいのでしょうか」
「レディ・ウァレンスが正式敬称でございます。申し遅れましたが、わたくしの名はイユルドゥ・カンドでございます。アッシュさまにおかれましては何(なに)についてもわたくしにお聞きくださいますようお願いいたします」
先ほどと同じ背の低いほうの色白の女官が答えた。低いといっても、小柄なアッシュの頭半分は高い。一七〇センチメートルくらいかしら。古の書を手にしているので文官だろう。ブロンド。
「では、レディ・ウァレンス。初めてお目にかかります。どうしてわたくしの名を知っておられるのですか?」
「レディに直接話しかけてはならない。——偉大な老賢者さまから知らせがあったのだ。しかし、ほんとうにこやつがアッシュさまなのか? もっとこう大きくて頼りがいのある……」
誰にでも理想はある。
「こちらはターユズ・アンゴ。武官なので口は良くないのですが、忠実なわたくしの守り手であり、親しい友人です。もちろんイユルドゥも」
照れて口をゆるめるターユズに、イユルドゥが空咳をした。規律。
「えーい、何かないのか、その身を証明するものは。偉大な老賢者さまから何か預かってはいないのか?」
左手で剣の柄頭を押さえながら訊いた。にじり、にじりよる。ダーク色の肌に威圧感があった。緑髪。
「老賢者さまからいただいたのは、この名だけです」
——偉大な老賢者さまからお名前をいただいた? アッシュの意味は確か……。
イユルドゥが古書を顎につけた。
「あっそれとこれも」
重い金貨を一袋、ターユズに渡した。
「うっ!」
一九〇センチメートル以上あるだろうターユズが落としそうになった。冷や汗をかきながら手にしているが全身が震えている。かわいい。
不思議に思ったアッシュが返してもらってお手玉すると普通の重さだった。確かに重いが、武官が落とすほどのことはなかった。ターユズ・アンゴの目が点になっていた。イユルドゥ・カンドは無表情。汝(なんじ)試すなかれ。
セジールが前に歩んだ。アッシュと顔が近い。
「アッシュさま。もっと近くに顔を……はいそうです」
背丈は同じくらいか、ヒールの分だけセジールのほうが高いかしら。
「わたくしの真名(まな)を伝えます。決して誰にも言ってはいけませんよ。わたくしの真(まこと)の名は——」
アッシュもいちおう真名(トゥルーネーム)ぐらいは知っていた。古の秘術では知られると、使役されるのだ。それを初対面で言うということは……。
「レッレディ!」
女官二名が青ざめた。恋は誰にも止められない。
エルゴまでは馬車で行くことになった。それまで馬車に乗ったことがなかったアッシュだったが、乗り心地は最高だった。
「魔術師による術が施されているのでございます。水と空気を組み合わせた高度な複合術でございます」
イユルドゥの説明は専門すぎてアッシュには理解できなかったが、要は人工的なエアサスペンションである。たとえるなら、フランスの自動車メーカーのシトロエンのハイドロニューマチック・サスペンションが近いだろう。かつては高級車ロールス・ロイスにも使われていた。
とはいえ、客人扱いとしても乗車定員6名の後部側に一人は奇妙な感じがした。進行方向に背を向けた席の中央はセジール、向かって左がイユルドゥだが、これは右のターユズの剣のためだろう。レディの隣では剣があたってしまうし、抜きにくい。いつもは二人分を使っていただろうターユズが身を小さくしていた。なっていないか。
——それにしても……。
内装がオール花柄だった。なお、サンドロ・ボッティチェッリの『プリマヴェーラ』に描かれているのは春(Primavera)の花である。
草の形に見覚えがあった。というより外に見えていた。
「この花の名は何というのですか?」
質問に答えていたイユルドゥが躊躇(ためら)った。
「クリスマス・ローズですわ、アッシュさま。もうすぐ花咲きます」
よどみなくセジールが答えた。会話の内容そのものよりアッシュと話をすることが好きなのだろう。
「なるほど……。どうして春に咲くのでしょう。花言葉は?」
「北の国から伝えられたと記録にございまして、北緯が高い国の冬至祭は春なのでございます。花言葉は——」
「——〈慈しみ〉〈労(いたわ)り〉〈追憶〉です」
セジールが言葉をつづけた。どうしても言いたかったのだろう。
「レディ」
たしなめられたセジールが口を曲げた。外見と同じく中身もまだ少女らしい。それもたしなめられ両手で口をおおった。
「王家の起(おこり)は北だと聞いている」
ターユズが剣を前に両手をそえて口にした。
「彼(か)の地から来訪したときに薬にしたのさ。それで助かった。おかげで私ターユズ・アンゴも此処(ここ)にいる。南方紛争のおり、裏切者にされた両親を助けてくれたのが今の辺境伯閣下なんだ。だから、私はレディの守り手を志願したんだ」
その決意を折ってしまった訳だ。アッシュは。
「ターユズが昔話をするときは〈誓い〉の再確認をしているのでございます」
「誓い? それは……いいえ別に説明はいりません」
不用意に人の心に入ってはいけない。知らず踏みにじる。
「〈誓い〉をたずねるのは不敬にあたるのでございます。たとえば、魂を賭(と)している場合は——」
「——あわわあわわ」
「イユルドゥ」
「はい?」
自分で言っていて気がつかなかったらしい。あわてているターユズと、名を呼ぶレディを交互に見たイユルドゥの顔が耳まで真っ赤になってうつむいた。
「アッアッシュさまの前ですと、つっつい心から話してしまうのでございます……」
友人を売るには十分な理由だった。#joke
アッシュの笑いについ三人もつられて笑ってしまった。
馬を御していた若い兵士も自然と笑顔になった。助手席の老兵がやれやれとうなずくのだった。
イユルドゥが古の書を開いた。
「こちらの記録によりますと、王家の起源は天空の彼方(かなた)だそうでございます。方舟(ジ・アーク)に乗って星から星に旅をしたのでございます」
「冗談じゃあない。空を飛ぶのだって魔術師十人でやっとなのに、そんなものあるはずがない」
いちおう飛行するものはあるらしい。
ターユズの知性はイユルドゥほど高くないにしろ、けっして低いほうではない。逆境を生き延びたのは運もあるが、ターユズ自身の機転のおかげだった。ただ、常識人ほど先入観に支配されてしまい、未知なるものは想像できないものだ。
アッシュの脳裏に、暗い宇宙に光の星の映像がうつった。まばたきする。
「……乗っていたかも」
「えっ?」
「はあ?」
「ご冗談を」
エルゴの街に到着すると巨大な門が左右に開かれていた。
——ドラゴンでも通るのかしら。
実際そうなのだが、アッシュはまだ知らなかった。門は二重になっており外門が橋として堀にかかっている。夜には閉めるのだろう。堀の底は深く、ときおりきらめくのは生物の目の光だった。落ちるのは遠慮したいところだ。
門をくぐると、広場になっており、神の一柱(ひとはしら)であるブルードラゴンが石のように眠っていた。有事にはその翼を広げ火を吐くのだが、今は頭上の雲が友だった。ゆるやかでも風があるのに庇雲(ひさしぐも)が移動していない。能力なのだろう。ドラゴンの戦いには雷雨が似合う。
馬車からターユズが先におり安全を確認してからイユルドゥとレディがおりた。ターユズが守れなくても、イユルドゥの身でレディは助かる。よほど信頼されているのだろう。
見惚(みと)れていたアッシュが足を踏み外してしまった。思わずレディに寄りかかってしまう。振り返ったセジールと唇を重ねそうになるが、次の瞬間アッシュはターユズの豊満な胸に顔をうずめていた。
自動発現した〈置換(サブスティテューション)〉だった。その身を代償にすれば身代わりとして、相手の傷を自分に負うことができる。
目をつむっていたセジールがゆっくり目をあけると、ターユズに蹴られたアッシュが飛んでいった。文字通り軽く二十メートルほど。芻狗(わらの犬)。
「死んだな」
「亡くなった」
居並ぶ兵士がことごとく口にした。元オウム(An Ex-Parrot)。
「アッシュさま!」
「あっ!」
レディの声でターユズが我に返った。イユルドゥは呆然と見ていた。書を紐解(ひもと)く。
「大丈夫か?」
走りよるターユズの顔から冷や汗が滝のように流れている。
「偉大な老賢者さまから庇護(ひご)を頼まれたアッシュさまを殺めてしまった……。どうしようどうしようどうしよう」
冷静に状況を楽しんでいるように見えなくもない。緊急事態では誰もが冷静ではいられない。冷静な人間がいるとすれば、それは訓練されているか、意図していたかどちらかだ。
「そうだ! そのまま堀に埋めてしまえばどうだろうか。アッシュさまは来なかった。そういうようにすれば万事うまくいく。そうだそうしよう」
バカだった。政治家には向いていない。
「口にでていますよ、ターユズ」
イユルドゥが忠告した。口に手をあてたがもう遅かった。
怒りのまま〈傾国の魔術師〉セジールが攻撃魔法〈反応消滅(リアクションデリート)〉を詠唱していた。もちろんこの傾国(けいこく)とは美しさから国を傾けるのではなく、実際に国が傾くほど被害がでる意味である。
「にっ逃げろ!」
「ってどこに?」
あたふたするのも無理はない。街の上に巨大な施術式が浮かび上がった。アッシュが見とれる。古の文字で装飾されており初めてみる者にとっては綺麗かもしれないが、術式を理解している人間からすれば、血も凍るような法術だった。〈反応消滅(リアクションデリート)〉は、熱反応から原子レベルから完全消滅させる。つまり灰も残らない。街はおろか一つの地方すべてが消えてしまうだろう。地図上からではなく、実際の風景として。
「困ったお嬢さまじゃて」
助手席にいた老兵が右義足を光り鳴らしながらセジールに後ろから近づくと肩にかるく手をやった。
びっくりして術式が中止され消えていく。ターユズの腰が抜けていた。
「ヤインズさま!」
イユルドゥに敬称で呼ばれたヤインズ・コルプフは、先(さき)まではレディの守護を任されていた。
「これではおちおち引退もできぬわい」
義足の守護印の光が消え、鳴り止んだ。
「よう見なされ、レディ・ウァレンス」
「やあ……」
そこには傷一つないアッシュが頭をかいて立っていた。てへ♩
しかし、問題が一つあった。「触らぬ神に祟りなし」という諺(ことわざ)をセジールお嬢さまは知らなかったらしい。——ブルードラゴンが目覚めていた。
「どうかしました?」
のんきにもほどがあるアッシュだが、誰もが危機感を予測できるとは限らない。それでも実際、危険になれば気づかないほうがどうかしている。
天空が雨雲で黒く染まっていく。稲光と雷鳴。
ブルードラゴンの影でようやくアッシュが見上げた。
「こんにちは」
物怖じせずアッシュがブルードラゴンに挨拶した。
〝Remember that you are dust, and to dust you shall return.〟
そう言うなりブルードラゴンが身をひるがえした。一陣の風で雲は散失し、青空の下に美女が立っていた。ピンヒール&美脚。ブルーアイズ&ブルーヘアー。豊胸&美声。
「老賢者(ザ・ワイズオールドマン)め。洒落(しゃれ)たことを。アッシュの意味を解(し)る神は従えだと?」
大変ご立腹のようである。次の瞬間、セジールの前に移動すると、レディの頬を右手の甲でぶった。当然、自動発現で〈置換(サブスティテューション)〉の身代わりのターユズの頬に傷がつくが、セジールの右頬からも血が流れていた。
「C、迂闊(うかつ)すぎる罰だ。Y、中央(セントラル)に案内(あない)せよ」
それぞれ、セジール・フォン・ウァレンスとイユルドゥ・カンドの真名の頭文字だろう。
「仰せのままに」
眉間にしわを重ねたイユルドゥが畏(かしこ)まって、先に街の中央(セントラル)にむかった。
「おのれ、レディに!」
ターユズだ。剣をもって立ち上がっている。
「お前はCが傷つけば魂を失うのだろう。万死に値する愚かさだな。では、Dの名のとおり〈不死(ノスフェラトゥ)〉を与えよう」
黒い霧がターユズ・アンゴをつつむと、アンデッド化がはじまった。傷が深まり頬がさけ歯が見えるがすぐに再生した。生と死の共存。
「来るな!」
アッシュが近よるが、ターユズが拒んだ。不死者にあっては生者は贄(にえ)になる。ターユズは両手で剣をまわし、自分の首を落とした。——が、まだ生きていた。
「何……だと……」
ターユズの言葉に、ブルーアイズが笑った。人間ではない神の思考は時として不可思議だった。
「アッシュ、教会につれて行け」
アッシュがまばたきして、自分を指さした。
「そうだ。Dの首を継(つ)げ。デュラハンにした覚えはないからな」
首無しデュラハンは、アイルランドに伝わる妖精で、正確には不死者(アンデッド)ではない。
「教会にプレイアがいる。PRだぞ、アッシュ」
頬に手をやるセジールの案内で、ブルーアイズが進んだ。若干、宙に浮いている。若い兵士が後退(あとずさ)った。
——ばっ化物(ばけもの)……。
正確には神であるが、人間には変わりないだろう。
「ムタク」
なすすべもなく見ていた若兵ムタク・カンユに、老兵ヤインズが声をかけた。
「ムタク・カンユ!」
ようやく我にかえるムタクだった。一方にセジールとブルーアイズ、もう一方にアッシュとターユズがいる。
「セジールさまにつけ。どおれ、わしはターユズをみてくる。他の兵は、命(めい)あるまで宿舎で待機だ」
「はっ!」
一礼すると、律ある兵隊がすっと片付けはじめた。ムタクがブルーアイズの後ろにつく。が……。
——おいおい、こいつ背後からでも威圧感(オーラ)があって近づけないぞ。
近づいてはならないパーソナルスペースが広く、おいそれと接近できなかった。
——ターユズの姉御があれだものおれが何の役にたつのやら……。ふう……。しかし、デカイな。
神胸である。歩いてはいないので揺れてはいないが、ムタクが見た誰よりも大きかった。
「ふう……すう……」
ヤインズが溜息をつくと、深呼吸にかえた。
「違う! そんなところをもつな!」
アッシュに抱かれたターユズの首が怒っていた。いちおう身体(からだ)も動かせるようだが、無線で遠隔操作をしているようなものだから上手に動かせないらしい。おまけに呪われているので、触れると生気を吸い取られる。それでいてアッシュは平気らしい。
「ほれ」
ヤインズがターユズの右手を、アッシュの左の肘上に掴ませた。視覚障害者の誘導だ。さすがは歴戦の勇者だけある。
「厄介な……」
懐から聖水をとりだすと、籠手(ガントレット)になじませた。侵食がとまる。
「ちょっと、歩みを合わせなさいよ」
その前では二人が二人三脚のようにぎこちなく歩いていた。
「困ったのお……」
ぜんぜん困った顔をせずヤインズがつぶやいた。
「もう大丈夫ですよ」
教会を目の前にしてアッシュが覗きこんだ。上からの視線になれていないターユズの首があさっての方向をむこうとして目を泳がせた。
「ぐはっ!」
入ったとたん、ターユズから白い煙がでた。崩壊しかけていた。神の〈呪(しゅ)〉による生と死の共存の均衡がやぶられたのだ。浄化により不死者(アンデッド)は本当の意味で死にいたるが、その生をとどめているのもまた〈不死(ノスフェラトゥ)〉という神の〈呪〉である。天使と悪魔の戦いのようなものかしら。
「マザー! マザー・ドハハユ!」
「おっ落ち着きなさい。シスター・ナネス」
女司祭(プリエステス)のドハハユ・オージャンと女助祭(ディーコネス)のナネス・クタハがパニックになっていた。
「まっまずは、浄化から行いましょう」
「死(ジ)ヴデジバヴダドヴガ!」死んでしまうだろうが!
祭壇におかれたターユズ(首)が怒っていた。頬が切れているので発音しにくい。
「これを使えませんか?」
アッシュが金貨の袋を出した。高貴な財は魔を制す。ナネスが受け取ったが、そのまま足に落とした。鈍い音。涙目のナネスをよそに、ドハハユが金貨を一枚だすがそれでもかなり重いらしくナネスの手をかりて、切断された首の上においた。もう一枚を首の下においてから、二人で首を持ち上げた。
「継(つ)いでちょうだい!」
金貨二枚がそれぞれ輝いた。
「おお!」
期待するヤインズだったが、次の瞬間、ターユズの首がぶっ飛んでいった。
「はーあー!」
シュール。
「磁石のようになっているのかしら?」
拾いにいったアッシュの予想は当たっていた。両方表面になっている。首下のコインを裏にして、アッシュがそっとおいた。
「うぎゃ!」
やはり光り輝いたが、顔が後ろに回転した。カラス神父。
継いだようにみえたが、同じように飛んでいった。
「あーーれーー!」
解帯。なお、実際に悪代官のように女性の帯を強引に解(と)くと、分解した昆布巻き状態になる。
ヤインズが受け止めた。重い。駆けよったアッシュがあずかり、角度を調節した。身体のほうのコインも微妙に動かした。
「もうちょい右だろうて。いやゆきすぎだ」
「いいえこのくらいで」
「マザー、違います。こうですって」
「お前ら遊んでいるだろう」
不思議とコインをつけている間は、ターユズの崩壊はとまっていた。傷はあるが、美しさがもどっていた。
「よかった。もとに戻りましたね」
ようやく継いだ首に金色(こんじき)の細いチョーカーが輝いていた。
「あの女……」
拳をにぎりしめた。
「やめんか。バカもの」
忿懣(ふんまん)やるかたないターユズの頭をヤインズがこづいた。かるく首が落ちた。
「きゃー!」
「ひえー!」
アッシュが受け止め、とびきりの笑顔をターユズに向けた。
「ありがと……」
照れている。
「どういたしまして」
それはそうとして……。
「あのう……」
アッシュが足を指さしながら、ナネスの顔をみた。
「うっぎゃーー!」
痛みを思い出したナネスの悲鳴が教会の外にも届いた。